Alles Gute zum Geburtstag, Osterreich
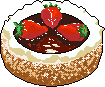

高嶺のクールビューティー
綺麗な顔をした男だとは思う。
でも、ただそれだけじゃないんや。
身にまとう雰囲気とか、やけに丁寧な口調とか、どこかずれた感覚とか。
とにかくオーストリアという男まるまる全部。
それが、人に綺麗だと思わせる。
そんでもって、ほんの少しひねくれた、というか、強情な部分があるもんだから、人によっては近寄りがたいなんて印象もプラスされるらしい。
俺にはよおわからんけど。
やって、あいつ、けっこう抜けとるし。
ぷりぷり怒っとるんも、結局照れてるだけやし。
何より。
「オーストリアー」
「なんです?」
「あんなーあんなー……」
「……スペイン?」
「あかん、忘れてもた」
「……………」
ふぅ、と小さく漏らされる溜息に、あははーと気にせず笑いかける。
「まったく、貴方は」
呆れたような台詞は、それでも、とてもやわらかい音。
ほんの少し眉尻を下げて、笑ってくれる。
こんな風に笑うことを知ったなら、誰も近寄りがたいなんて言わないだろうに。
まあ、知らせてやる必要なんてないんやけどな!
君の笑顔が見てみたい
「あなたはまたお馬鹿な事を!反省なさい!」
「あーもう、うっせぇ―っ!」
頭からポコポコと湯気を立てる坊ちゃんに、うんざりと怒鳴り返す。
大した事はしてねぇっていうのに、本当にうるさいったらありゃしねぇ。
俺様のすることが気にいらねぇなら、いっそ放っておいてくれりゃあいいのに。
「同じ台詞を何度言わせたら気が済むのですか、本当にもう…」
そう言って、ふぅっと溜息をついて見せてくる。
「俺だって、お説教は聞き飽きたっつうの!」
毎度毎度、厭味ったらしく小言を言ってきやがって。
お前は俺の母親か、それとも、彼女か。
「あ」
「……?」
「お前、もしかして俺のこと好きなのか?」
「いっ…!」
じんじんと痛む頬を押さえて、にじむ涙を必死にこらえる。
非力な癖に、なんであんな強烈なビンタができんだよ…!
「あーもー…」
別に怒らせたいわけじゃなかった。
なんとなく、思いついた事を言ってしまっただけで。
「いってぇなー…」
いつもいつも俺の前では、怒った顔ばかり。
俺のことを好きになれなんて言わねぇから。
「せめて笑えよ、ちくしょー…」
斜に構えたその横顔
最後にあやつの目をまっすぐに見たのはいつのことだったか。
お互いに好き好んで顔を合わせることもない。
偶然出会ってしまっても、眉をひそめて視線をそらす。
それに不満を覚えることなどない。
過去の思い出にとらわれるなど馬鹿げたことだ。
こちらを見る瞳の色も。
やわらかな笑顔も。
背中に預けられた温かな体温も。
全て、忘れた。
忘れ去ったはずだった。
「貴方からお誘いを受けるとは思いませんでした」
目の前に座る男が、感情を感じさせない声で静かに呟いた。
返事を返さないこちらに、長い指が退屈を紛らわすようにカップの淵をなぞる。
「…来るかどうか、大変迷ったのですが」
最初、悪戯かとすら思いました。
そう付け加える言葉に、確かにと納得する。
自分でさえ、どうして今更この男を誘おうと思ったのか、理解できていないのだから。
「でも」
そう言葉を切って、相手は口を閉ざした。
二人きりの部屋の中、窓辺からそよぐ風の音だけが響く。
「来てよかった」
小さく小さく、こちらまで届くギリギリの声で落とされた言葉。
それに、ハッと顔を上げさせられる。
目に映るのは、窓の向こうを眺める横顔。
不思議にやわらかいその表情に、心のどこかで安堵する。
同時に、けしてこちらには向けられない視線に、ひどく胸が痛んだ。
では試しに挨拶から
お上品なお貴族様は、どうやら軽薄な男はお嫌いなようで。
俺自慢の口説き文句も、最高に決めた流し目も、氷のような視線に阻まれた。
さてさて、と一旦体制を立て直すように息を吐く。
こんなことくらいでめげたりしない。
簡単に諦めるようでは、愛の国の名折れだからね。
それに、一筋縄ではいかない方が、燃えるってもんだろう?
「だからね、俺はやめないよ?」
「………本当に、貴方は物好きですね」
隣に座る苦みばしった相手の顔を、覗き込むように笑いかける。
顔に触れようと伸ばした手を、ごくごく自然に避けられた。
そのまま、詰めていた距離をさっと広げられる。
うーん、これはなかなか手ごわい。
「じゃあさ、どんな風にしたら相手してくれる?」
もう一度、二人の間の隙間をなくして、すぐ隣の位置を陣取る。
ごく近い距離に露骨に嫌そうな顔をされても、気にしない。
「……そうですね」
あきらめたような溜息とともに、視線がこちらを向けられる。
にこり、と非の打ちどころのない笑みを向けられて、こちらも自然笑みを作るのはもう条件反射。
「少なくとも、冗談を真に受けるような趣味はありませんので」
切り捨てるようなその一言に、引きとめられる隙はなく。
足早に立ち去る背中を、ただぼんやりと見送った。
「冗談ねぇ…」
確かに、こうして口説いているのも、半分遊びのようなものだけど。
「じゃあ、本気になったら相手してくれるの?」
小さくなっていく背中に、にやりと唇を歪ませる。
この俺が本気になったなら。
冗談だと切り捨てる、逃げ道なんか与えてやらない。
「それもおもしろいかもなぁ」
真剣に、誠実に、この俺以外見えないように。
まず、手始めは挨拶から。
「さぁて、ショウの始まりだ」
ほら、笑うとこんなに
怒っていたり、不機嫌だったり、無表情だったり。
そう言えば、笑ったところを見ることが少ない、とふいに気付いた。
長く傍にいた癖にそれはどうなのだろう。
かといって、意識して人を笑わせようとするなど、あまりにも不得手すぎる。
どうしたらいいか悩んで、悩んで、悩んで。
結局。
「どうしたらお前は笑ってくれる?」
本人に直接聞いてみた。
「……………」
ぽかん、とまるく開いた口。
煮詰まったとはいえ、やはり本人に聞くようなものではなかったか。
こんな表情も珍しいな、と半ば投げやりな頭で考える。
「ふっ」
今すぐこの場から逃げ出したい、そう考えた所で、小さく空気の漏れるような音。
ハッと顔を上げて見れば、おかしくてたまらないといったように声をあげて笑いだす。
「あはは、はは!」
「な…っ!そんなに笑うことないだろう…っ!」
「だって、ドイツ、貴方…ふふっ」
ああ、今俺はひどく赤い顔をしていることだろう。
どうしようもない恥ずかしさに殺されそうになりながら、必死で耐える。
未だ笑いを収めきれずにいる相手をそっと盗み見ると、目尻にたまった涙を拭おうと眼鏡に手をやっていた。
死にそうな程に恥ずかしいけれど、目的は果たされたのにヨシとする。
「やはり、笑っている方がいい…」
そうポツリ呟けば、漏れる笑い声がぴたり止まって。
「どこでそんな台詞覚えてきたんです…」
勢いよく赤く染まった顔に、そんな風に詰られた。
そう言えば、笑ったところを見ることが少ない、とふいに気付いた。
長く傍にいた癖にそれはどうなのだろう。
かといって、意識して人を笑わせようとするなど、あまりにも不得手すぎる。
どうしたらいいか悩んで、悩んで、悩んで。
結局。
「どうしたらお前は笑ってくれる?」
本人に直接聞いてみた。
「……………」
ぽかん、とまるく開いた口。
煮詰まったとはいえ、やはり本人に聞くようなものではなかったか。
こんな表情も珍しいな、と半ば投げやりな頭で考える。
「ふっ」
今すぐこの場から逃げ出したい、そう考えた所で、小さく空気の漏れるような音。
ハッと顔を上げて見れば、おかしくてたまらないといったように声をあげて笑いだす。
「あはは、はは!」
「な…っ!そんなに笑うことないだろう…っ!」
「だって、ドイツ、貴方…ふふっ」
ああ、今俺はひどく赤い顔をしていることだろう。
どうしようもない恥ずかしさに殺されそうになりながら、必死で耐える。
未だ笑いを収めきれずにいる相手をそっと盗み見ると、目尻にたまった涙を拭おうと眼鏡に手をやっていた。
死にそうな程に恥ずかしいけれど、目的は果たされたのにヨシとする。
「やはり、笑っている方がいい…」
そうポツリ呟けば、漏れる笑い声がぴたり止まって。
「どこでそんな台詞覚えてきたんです…」
勢いよく赤く染まった顔に、そんな風に詰られた。




